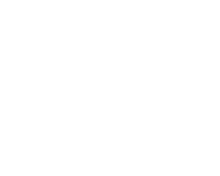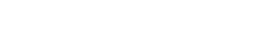SUS316は磁性がある?非磁性ステンレスの誤解と対策を徹底解説
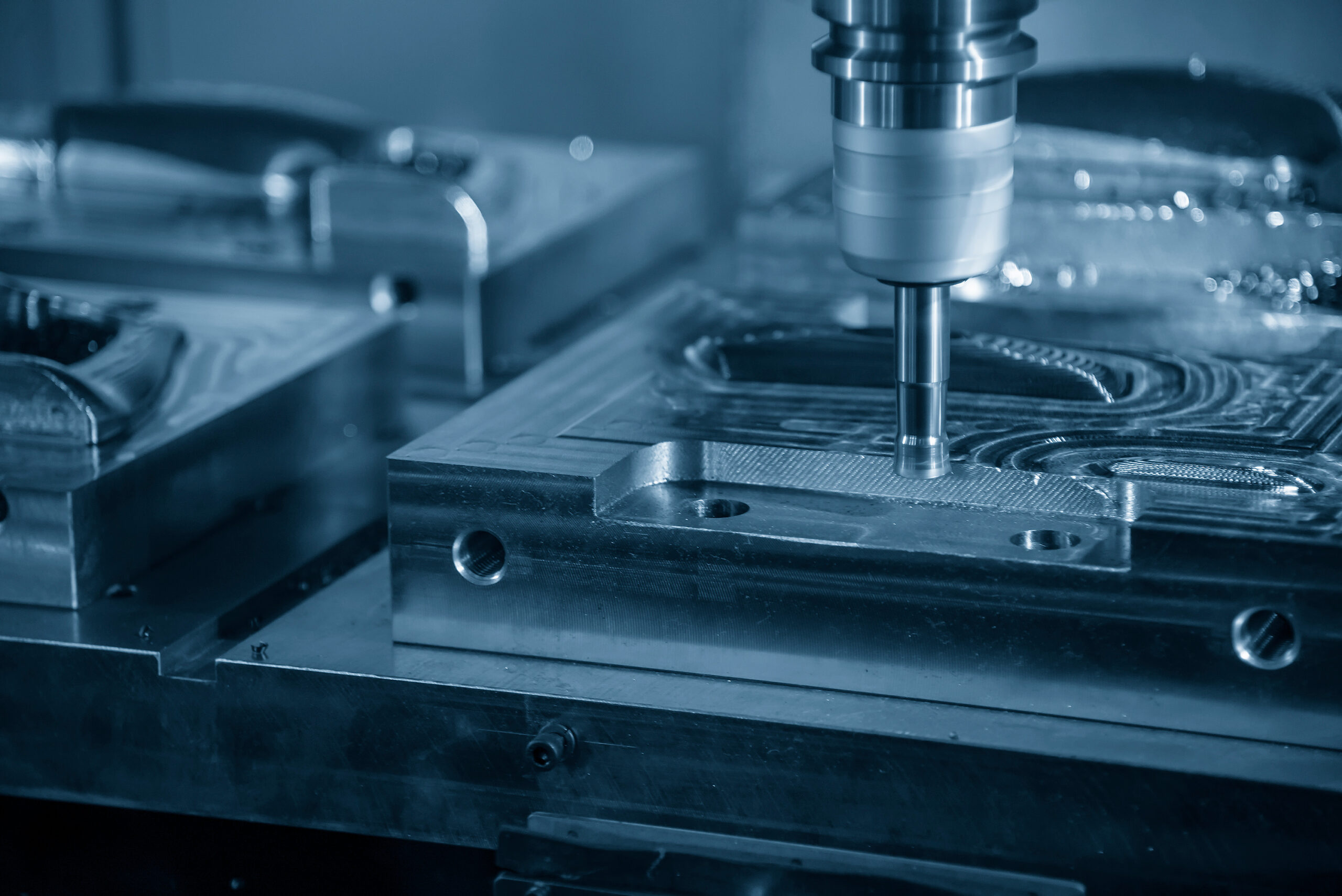
SUS316は磁性がある?非磁性ステンレスの誤解と対策を徹底解説
SUS316は「非磁性ステンレス」として知られていますが、実際に磁石を近づけると「うっすらと吸い付く」ことがあります。
この記事では、SUS316の磁性がどのように生じるのか、その原因・防止方法・用途ごとの注意点を
材料学的な観点から詳しく解説します。
SUS316とは?オーステナイト系ステンレスの代表格
SUS316は、クロム(Cr)16〜18%、ニッケル(Ni)10〜14%、モリブデン(Mo)2〜3%を含むJIS規格のオーステナイト系ステンレス鋼です。
耐食性に優れ、特に塩化物環境下での耐孔食性に強いため、海水環境や医療機器、化学装置など幅広く使用されています。
| 成分 | 含有量(%) | 役割 |
|---|---|---|
| Cr | 16.0〜18.0 | 耐食性向上 |
| Ni | 10.0〜14.0 | オーステナイト組織安定化 |
| Mo | 2.0〜3.0 | 耐孔食性・耐酸性向上 |
同系統のSUS304と比較すると、SUS316はモリブデン添加によってより高い耐食性を持ちます。
SUS304との違いについては、「SUS304とSUS316の違いに関して解説」で詳しく説明しています。
なぜ「非磁性」のはずのSUS316が磁石に反応するのか?
オーステナイト系ステンレスは理論上非磁性ですが、冷間加工や溶接によって組織の一部が変化し、マルテンサイト変態が生じることがあります。
これが「磁性を帯びる」原因です。
磁性発生の主な原因
- 冷間加工:圧延や曲げなどによるひずみでマルテンサイト組織が生成。
- 溶接熱影響:高温冷却の際にフェライト組織が一部生成。
- 異材溶接:SUS316とフェライト系鋼が混在すると磁化が局所的に発生。
つまり、素材自体が磁性を持っているわけではなく、「加工や熱履歴」が磁性を誘発するのです。
磁性が発生した場合の確認と対策
もしSUS316製品に磁性が見られる場合は、以下のような方法で確認と対処が可能です。
| 方法 | 目的 | 概要 |
|---|---|---|
| 磁気検査 | 磁化状態の定量化 | ガウスメーターで表面磁束密度を測定 |
| 溶体化処理 | 磁性除去 | 約1050℃で加熱後急冷し、マルテンサイトを再オーステナイト化 |
| 機械加工軽減 | 磁性発生抑制 | 成形後の追加加工を最小限にする |
特に、医療・半導体・真空装置分野では磁性の有無が製品性能に直結するため、
熱処理工程の最適化が重要です。
磁性の有無が問題となる用途と注意点
磁性の発生が問題となる主な分野は以下の通りです。
- 医療用器具(MRI対応部品)
- 電子機器内部構造(磁界の乱れ防止)
- 真空装置(磁場干渉の防止)
これらの分野では、非磁性保持のために「溶体化処理」や「完全オーステナイト材(316L)」を選定することが推奨されます。
SUS316Lに関しては「SUS316Lの特性と用途に関して解説」で詳しく取り上げています。
磁性対策としてのSUS316Lと他素材の比較
SUS316の低炭素版であるSUS316Lは、炭素量を0.03%以下に抑えることで、
溶接時の炭化物析出を防ぎ、より安定した非磁性を維持できます。
| 鋼種 | 磁性 | 耐食性 | 用途 |
|---|---|---|---|
| SUS304 | 弱磁性(加工後) | 標準 | 建築部材・厨房機器 |
| SUS316 | 弱磁性(加工後) | 高 | 化学装置・船舶部品 |
| SUS316L | ほぼ非磁性 | 非常に高い | 医療機器・半導体装置 |
より詳細な鋼種比較は「ステンレス鋼の種類比較に関して解説」でまとめています。
よくある質問(FAQ)
SUS316は基本的にオーステナイト系ステンレスのため非磁性ですが、冷間加工や溶接などで部分的に磁性を帯びることがあります。これはマルテンサイト変態によるもので、加工条件や熱処理工程に依存します。非磁性を維持したい場合は、低炭素タイプのSUS316Lを選ぶと良いでしょう。SUS316Lの特性については「SUS316Lの特性と用途に関して解説」で詳しく紹介しています。
はい、溶体化処理を行うことで再び非磁性状態に戻すことが可能です。おおよそ1050℃で加熱後、急冷することでマルテンサイトがオーステナイトに再変態します。この処理により、磁性を除去し安定した組織を得られます。
SUS316の磁性は、医療機器(特にMRI対応部品)や半導体装置、真空機器など磁場の影響を受けやすい分野で問題となります。これらの用途では磁界の乱れを防ぐために完全非磁性材料が求められます。そのためSUS316Lやチタン合金などの選定が推奨されます。
まとめ:SUS316の磁性は「加工条件」で変化する
SUS316は本来非磁性のステンレスですが、冷間加工・溶接・応力によって部分的に磁性を帯びることがあります。
ただし、溶体化処理やSUS316L材の選定により、再び非磁性を確保できます。
用途ごとの特性を理解し、適切な処理を施すことが、長期的な品質と信頼性の確保につながります。